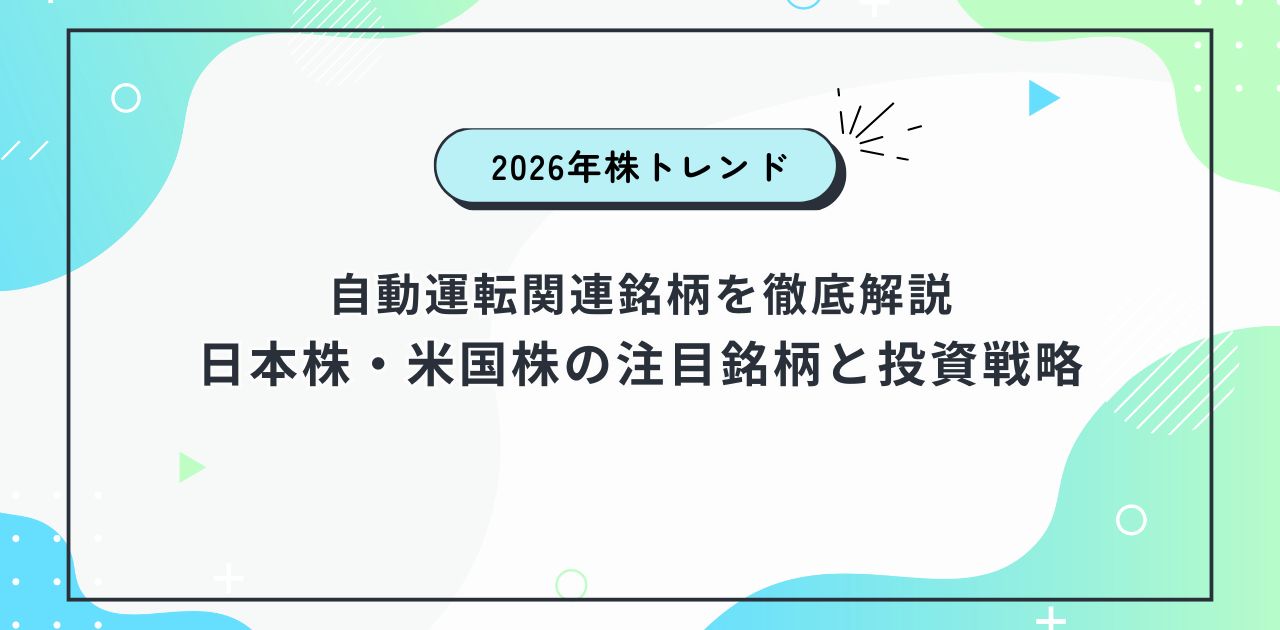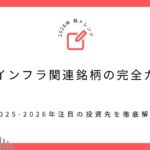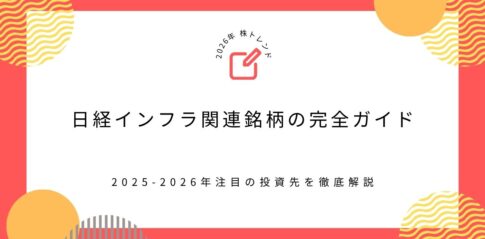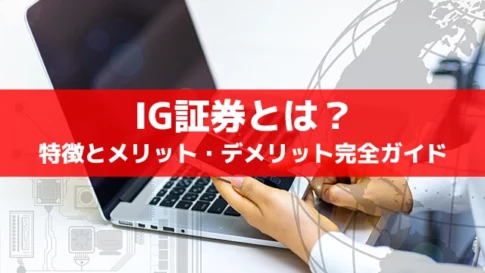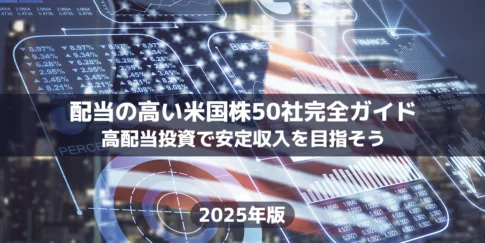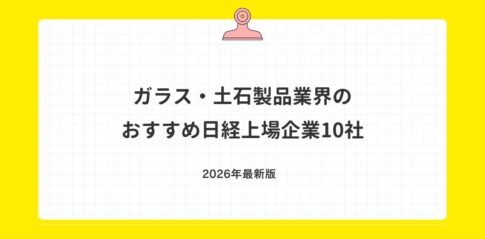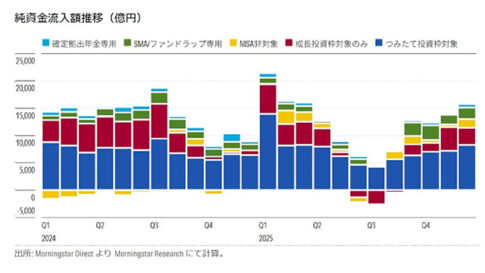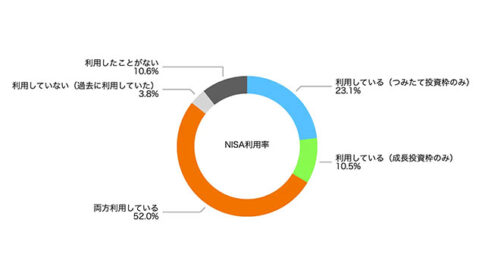自動運転市場の現状と将来性
急成長する自動運転市場
自動運転技術は、21世紀を代表する革新的テクノロジーとして世界中から注目を集めています。2030年には20兆円規模のメガマーケットが創出されるとの試算もあり、投資家にとって見逃せない成長分野となっています。
日本政府は2025年をめどに全国40カ所、2030年までに100カ所以上でレベル4の無人自動運転移動サービスの実現を目標に掲げています。また、2025年にはトラックによる物流サービスや高速道路での自家用車のレベル4走行の実現も目指しており、法整備と技術開発が急速に進んでいます。
米国での実用化が加速
一方、米国では既にAlphabet傘下のWaymoやGM傘下のCruiseが、サンフランシスコやロサンゼルス、フェニックスなどでレベル4の自動運転タクシーサービスを商用化しています。2025年8月にはWaymoがニューヨークでの試験走行を開始するなど、実用化が急速に進展しています。
中国市場の台頭
中国でもBaidu(百度)やPony.aiといった企業が複数の都市で自動運転タクシーの商用化を開始しており、世界的な開発競争が激化しています。
自動運転のレベル分類と技術動向
自動運転レベルの定義
自動運転技術は0から5までの6段階に分類されています。投資判断をする上で、各企業がどのレベルの技術開発を進めているかを理解することが重要です。
- レベル0:運転自動化なし
ドライバーがすべての運転操作を実行 - レベル1:運転支援
システムが速度調整またはハンドル操作のいずれかを支援 - レベル2:部分運転自動化
システムが速度調整とハンドル操作の両方を同時に支援(例:テスラのオートパイロット、GMのスーパークルーズ) - レベル3:条件付運転自動化
特定条件下でシステムが全ての運転操作を実行するが、緊急時にはドライバーの対応が必要 - レベル4:高度運転自動化
特定条件下でシステムが全ての運転操作を実行し、ドライバーの介入は不要 - レベル5:完全運転自動化
あらゆる条件下でシステムが全ての運転操作を実行、運転席すら不要
現在の技術到達点
2025年10月時点で、商用化されているサービスの多くはレベル4に分類されます。テスラは2024年10月に自動運転タクシー「サイバーキャブ」を発表し、2026年から2027年の生産開始を目指していますが、完全なレベル5の実用化はまだ先の話となっています。
日本株の注目自動運転関連銘柄
自動車メーカー
トヨタ自動車(7203)
日本を代表する自動車メーカーであるトヨタは、「Mobility Teammate Concept」の理念のもと、高度安全運転支援システム「ガーディアン」と自動運転システム「ショーファー」の開発を進めています。
子会社のウーブン・プラネット・ホールディングスと米国のトヨタ・リサーチ・インスティチュート(TRI)が最先端技術の開発を担当。2024年には実証都市「Woven City」の第一期工事が完了し、今年、2025年から実証がスタートしました。
MaaS活用を前提とした自動運転車「e-Palette」の実用化にも注力しており、ソフトウェアプラットフォーム「Arene(アリーン)」の実用化も2025年を予定しています。また、お台場の一部でレベル4のロボタクシーを計画中で、2025年以降は都心への拡大を目指しています。
ホンダ(7267)
ホンダは米GMおよびCruiseと3社パートナーシップを結び、日本での自動運転タクシー事業を2026年初頭に開始する計画を進めています。これが実現すれば、日本初の本格的な自動運転タクシーサービスとなる可能性があります。
また、ソニーとの共同出資会社「ソニー・ホンダモビリティ」を通じて、次世代の自動運転技術開発にも取り組んでいます。
日産自動車(7201)
日産は国内生産の再編に取り組んでいますが、独自の自動運転技術開発を進めるとともに、Waymoとも提携関係にあり、グローバルな技術協力体制を構築しています。
部品・システムサプライヤー
住友電気工業(5802)
2025年の大阪・関西万博における会場への来場者輸送を見据えた「自動運転レベル4」の実証実験に参画しました。
自動運転車では高性能なセンサーの増加により、ワイヤハーネスの高機能化が重要となりますが、住友電気工業は高速・大容量通信と軽量化を両立する車載光ハーネスの開発を進めており、自動運転のインフラ技術で重要な役割を担っています。
ソニーグループ(6758)
ソニーはCMOSイメージセンサー技術で世界トップクラスの競争力を誇ります。イメージセンサーはカメラのレンズから入った光を電気信号に変えてデータ転送する半導体で、自動運転技術に必要不可欠な「車の目」に相当する重要部品です。
距離情報を含む3Dセンサー技術も開発しており、車載イメージセンサーやセンシング技術は自動運転でほぼ必須となる見込みです。ホンダとの共同出資会社「ソニー・ホンダモビリティ」でも自動運転技術を開発しています。
ソフトウェア・システム開発企業
アイサンテクノロジー(4667)
自動運転分野のソフトウェア開発で注目される企業です。2023年2月に三菱商事と共同で、自動運転ワンストップサービスを提供する新会社「A-Drive」を設立しました。
自動運転車両に必要な機器・システム・インフラ設備の調達支援や、自動運転車を運行するためのコンサルティングサービスを提供しており、自動運転の実用化を総合的に支援する体制を構築しています。
イーソル(4420)
組み込み機器に特化したOS(基本ソフト)の開発販売が主力事業です。2021年7月に、自動運転技術開発のスタートアップであるティアフォーと戦略的パートナーシップを締結しています。
世界初のオープンソース自動運転ソフトウェア「Autoware(オートウェア)」を利用した自動運転技術の商用化と普及を加速させることを目指しており、2015年のオートウェア立ち上げ時からプロジェクトに参画。関連OSを用いた実車実験などで共同開発を実施しています。
デンソー(6902)
トヨタグループの中核部品メーカーとして、自動運転に必要な先進運転支援システム(ADAS)の開発・製造で世界的に高いシェアを持っています。カメラ、レーダー、LiDARなどのセンシング技術に強みがあり、自動運転の「目」となる重要部品を供給しています。
AIを活用した画像認識技術や、車両の周辺環境を高精度で認識するセンサーフュージョン技術の開発にも注力。トヨタの自動運転開発においても重要なパートナーとして協力関係を築いており、レベル4以上の自動運転実現に向けた技術開発を推進しています。
ソリトンシステムズ(3040)
セキュリティ対策ソフトやシステム構築が経営の柱です。2021年7月に経済産業省が公募した「無人自動運転等の先進MaaS実装加速化推進事業」の委託先に採択されています。
2024年12月には名古屋大学などと新しい遠隔型自動運転システムを開発したと発表。生活道路での路上車両運転の迂回など、自動運転での対応が難しい走行ケースに対して、簡易な操作で補完・支援できるシステムを実用化しています。静岡県での小型バスなどで、遠隔型自動運転に関する公道実証実験の実績を有しています。
AI・半導体関連企業
HEROZ(4382)
AI技術を活用した自動運転開発に注力しています。2022年7月に完全自動運転の実現を目指す自動運転AIアルゴリズム開発スタートアップのTURINGに出資し、自動運転技術の開発や走行実験・走行データ取得に関与しています。
Kudan(4425)
3D空間認識技術を持つ企業で、2022年7月に中国で自動運転ソリューションを開発するWhale DynamicがKudan 3D-Lidar SLAM技術を統合した自律走行型配送車を開発するなど、国際的な展開を進めています。
4. 米国株の注目自動運転関連銘柄
自動運転プラットフォーム企業
Alphabet(GOOGL)- Waymo
Alphabetの子会社Waymoは、自動運転分野で世界をリードする企業です。米国で唯一商業ベースの完全自動運転タクシー「Waymo One」を運行しており、アリゾナ州フェニックス、カリフォルニア州ロサンゼルス、サンフランシスコで既にサービスを展開しています。
2025年8月にはニューヨークでの試験走行を開始するなど、事業エリアを着実に拡大中です。Uberアプリからも利用可能になるなど、利便性の向上にも注力しています。
技術面では、親会社が自動車メーカーでない点が強みの一つとなっています。自動運転技術を自前で開発していないメーカーに提供することで、業界標準を目指しており、フィアット・クライスラー・オートモービルズ(FCA)、日産、ルノー、ボルボ・カー、ジャガー・ランドローバーとも提携しています。
2025年には日本でも配車アプリ大手のGOや日本交通と組んで、東京都内で自動運転技術の実証を開始する計画を発表しており、グローバル展開を加速させています。
自動車メーカー
テスラ(TSLA)
世界最大級の電気自動車メーカーで、自動運転技術でも業界をリードしています。2024年10月に自動運転タクシー「サイバーキャブ」と20人乗りの「ロボバン」を発表し、2026年から2027年の生産開始、価格は3万ドル(約445万円)以下を目指すとしています。
テスラの自動運転アプローチは、LiDAR(ライダー)を使わずカメラとAIのみで実現する点が特徴です。現在のレベル2+の「オートパイロット」から、2025年末までに米国のいくつかの都市で「FSD Unsupervised(監視不要の完全自動運転)」が利用可能になるとCEOのイーロン・マスク氏は語っています。
ゼネラル・モーターズ(GM)
米国自動車メーカー大手のGMは、傘下のCruiseを通じて自動運転タクシー事業を展開しています。CruiseはホンダとともにGMのパートナーとなり、日本でも2026年初頭に自動運転タクシーサービスを開始する計画です。
2023年10月に人身事故を起こし一時サービスを中止しましたが、現在はテキサス州ヒューストンやダラス、アリゾナ州フェニックスでセーフティドライバー同乗のもと公道実証を再開しています。日本やドバイでも自動運転タクシーサービスの導入が計画されており、今後の展開が注目されます。
本業である自動車販売も好調で、ハンズフリー運転が可能なレベル2+の「スーパークルーズ」を複数車種に搭載しています。
フォード(F)
米国ビッグスリーの一角を占める老舗自動車メーカーです。コネクテッド技術や自動運転、MaaSの研究開発を手掛ける子会社「Ford Smart Mobility」を2016年に設立し、2018年には自動運転開発部門を分離して「Ford Autonomous Vehicles」を設立しています。
過去にはスタートアップArgoAIに出資しテクノロジーパートナーとして関係を深めていましたが、同社は2022年に閉鎖されました。現在は独自の路線で自動運転技術の開発を継続しています。
半導体・センサー関連企業
Intel(INTC)- Mobileye
半導体世界大手のIntelは、2017年に買収したMobileyeを通じて自動運転分野に参入しています。Mobileyeは運転支援システム(ADAS)および自動運転技術の開発で世界をリードする企業で、多くの自動車メーカーに技術を供給しています。
NVIDIA(NVDA)
AI半導体のリーダーであるNVIDIAは、自動運転車のプラットフォーム「NVIDIA DRIVE」を提供しています。高性能なGPUとAI処理能力により、自動運転に必要な膨大なデータ処理を可能にしており、多くの自動車メーカーが採用しています。
Ouster(OUST)
高性能デジタルLiDARセンサーを開発する企業です。従来のアナログ方式ではなく、デジタル方式のLiDAR技術を採用することで、高解像度、長距離検知、低コストを実現しています。
自動運転車両だけでなく、産業用ロボット、スマートインフラ、ドローンなど幅広い分野への応用が可能で、市場の拡大が期待されています。独自のデジタルLiDAR技術により、従来製品よりも小型化と高性能化を両立し、次世代の自動運転センサーとして注目を集めています。
Innoviz Technologies(INVZ)
BMWなどと提携するLiDAR開発企業です。固体型LiDARの開発に注力しており、コスト削減と高性能化を両立する技術で注目を集めています。
MicroVision(MVIS)
ホログラフィックLiDAR技術を開発するメーカーです。独自の技術により、従来よりも高解像度で長距離検知が可能なLiDARを提供しています。
Analog Devices(ADI)
LiDARやADAS向けアナログIC製造を手掛ける半導体メーカーです。自動運転に必要なセンサー技術の基盤を提供しています。
新興自動運転企業
Cyngn(CYN)
自動運転物流プラットフォームを開発する企業です。工場や倉庫など限定された環境での自動運転車両の実用化に注力しています。
Knightscope(KSCP)
セキュリティロボット企業として知られ、自律移動技術を警備分野に応用しています。自動運転技術の多様な用途展開を示す事例として注目されます。
Indie Semiconductor(INDI)
ADAS用半導体開発を専門とする企業です。先進運転支援システムに必要な半導体チップを自動車メーカーに供給しています。
投資する際のポイントと注意点
技術開発段階の確認
自動運転関連銘柄に投資する際は、各企業がどのレベルの技術開発に取り組んでいるかを確認することが重要です。レベル2からレベル4への移行、レベル4からレベル5への移行には技術的なハードルがあり、実用化までの時間軸が大きく異なります。
事業収益化の見通し
多くの自動運転開発企業は現在も赤字ベースで運営されています。Waymoのように既に商用化を開始している企業でも、黒字化までには時間がかかる見込みです。投資判断では、企業の財務体力と収益化までのロードマップを慎重に評価する必要があります。
規制動向への注視
自動運転の実用化には法整備が不可欠です。2025年、米運輸省は自動運転に関する国家戦略を発表し、過剰な規制を撤廃する方針を明らかにしました。このような規制環境の変化は、関連銘柄の株価に大きな影響を与える可能性があります。
日本でも2023年に改正道路交通法が施行され、レベル4の自動運転が可能になるなど、法整備が進んでいます。各国の規制動向を継続的にフォローすることが重要です。
競合関係と提携戦略
自動運転分野では、自動車メーカー、テック企業、部品メーカーなど多様な企業が競合しながらも提携関係を構築しています。例えば、WaymoとUberの提携、GMとホンダの協力関係など、企業間の戦略的関係が事業展開に大きく影響します。
地域別の成長性
米国、中国、欧州、日本など、地域によって自動運転の実用化ペースが異なります。米国と中国が先行し、日本は後れを取っている状況ですが、今後の巻き返しも期待されます。グローバルな視点で投資先を選定することが重要です。
リスク要因の理解
自動運転技術には以下のようなリスク要因があります。
- 技術的課
悪天候や複雑な交通状況への対応など、解決すべき技術課題が残っています - 安全性の証明
人身事故が発生した場合、社会的な信頼を失い事業に大きな影響が出る可能性があります - 高額な開発コスト
継続的な巨額投資が必要で、財務体力の弱い企業は淘汰される可能性があります - 法的責任問題
事故発生時の責任の所在など、法的な枠組みが完全には整っていません
分散投資の重要性
自動運転分野は高成長が期待される一方、リスクも高い投資先です。特定の銘柄に集中投資するのではなく、自動車メーカー、プラットフォーム企業、部品メーカー、半導体企業など、バリューチェーン全体に分散投資することでリスクを軽減できます。
まとめ:自動運転銘柄への投資戦略
長期的な視点での投資
自動運転技術の本格的な普及には、まだ数年から10年程度の時間がかかると予想されます。短期的な株価変動に一喜一憂せず、長期的な成長を見据えた投資姿勢が重要です。
2030年に20兆円規模(※1)の市場が創出されるという試算は、現在の数倍から数十倍の成長を意味します。この成長の果実を享受するためには、早期から有望銘柄に投資し、じっくりと育てる戦略が有効です。
日本株と米国株の組み合わせ
日本株では、トヨタやホンダなどの自動車メーカー、ソニーや住友電気工業などの部品・システムサプライヤー、イーソルやアイサンテクノロジーなどのソフトウェア企業が注目されます。
米国株では、WaymoやTesla、GMなどの自動運転開発をリードする企業に加え、NVIDIAやIntelなどの半導体企業、各種LiDARメーカーなど、幅広い選択肢があります。
日本株と米国株を組み合わせることで、地域分散とバリューチェーン分散の両方を実現できます。
今後の注目ポイント
2025年から2026年にかけて、以下の動きが注目されます。
- トヨタのWoven City実証開始(2025年)
- テスラのサイバーキャブ生産開始(2026~2027年予定)
- GMとホンダの日本での自動運転タクシーサービス開始(2026年初頭予定)
- Waymoの日本での実証開始(2025年予定)
- 日本でのレベル4自動運転の本格展開(2025年以降)
これらのマイルストーンは、関連銘柄の株価に大きな影響を与える可能性があります。
最終的な投資判断
自動運転関連銘柄への投資は、将来の社会インフラを支える技術への投資でもあります。市場規模の拡大、技術の進歩、法整備の進展など、多くのポジティブな要因がある一方で、技術的課題や安全性の証明、激しい競争など、リスク要因も存在します。
投資家は、自身のリスク許容度と投資期間を考慮しながら、複数の銘柄に分散投資することで、この成長市場の恩恵を享受する戦略を検討すべきでしょう。
自動運転技術は、単なる技術革新にとどまらず、モビリティの概念を根本から変える可能性を秘めています。高齢化社会における移動手段の確保、物流効率の向上、交通事故の削減など、社会的な意義も大きく、長期的な投資先として魅力的な分野といえます。
免責事項:本記事は情報提供を目的としており、特定の銘柄の購入を推奨するものではありません。投資判断は自己責任で行ってください。株式投資にはリスクが伴い、元本割れの可能性があります。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。