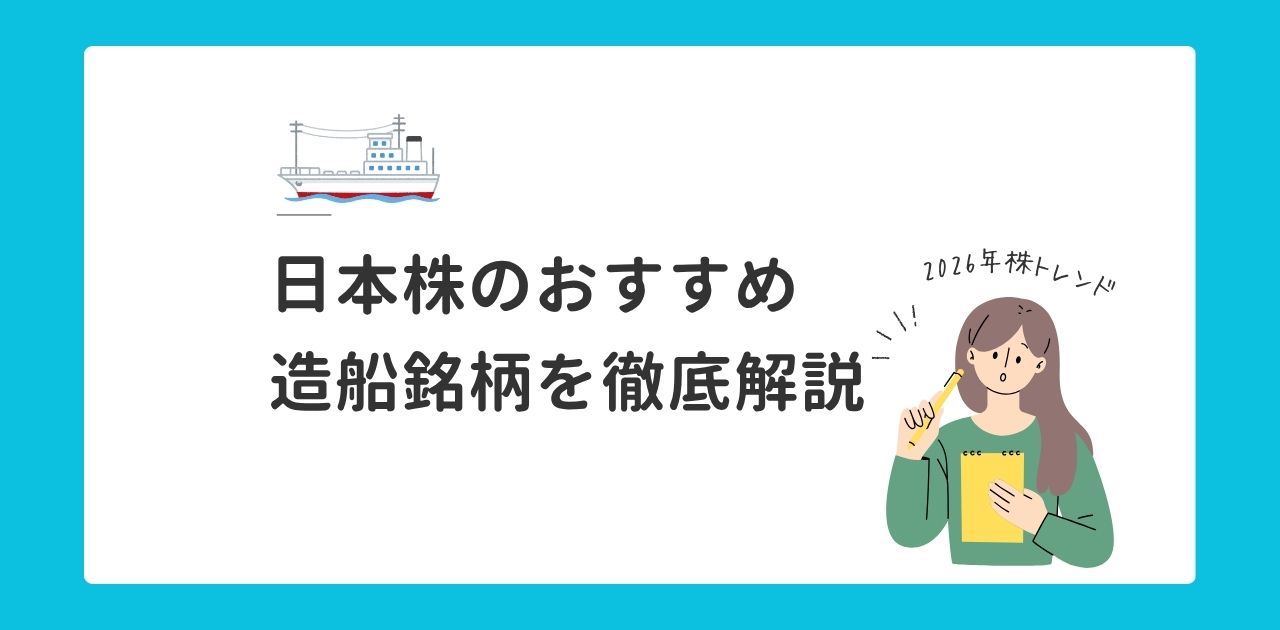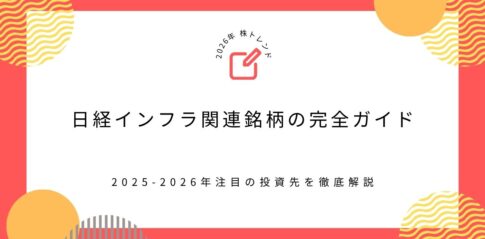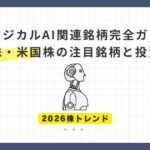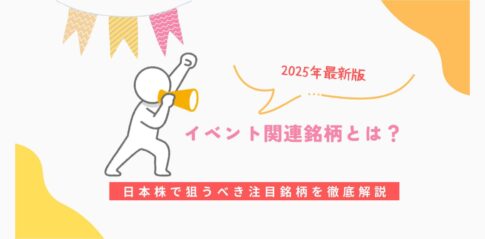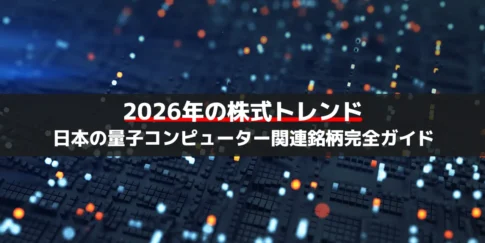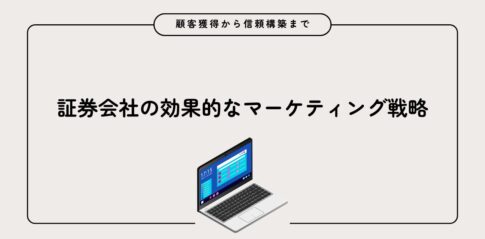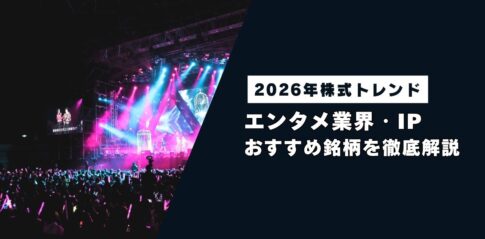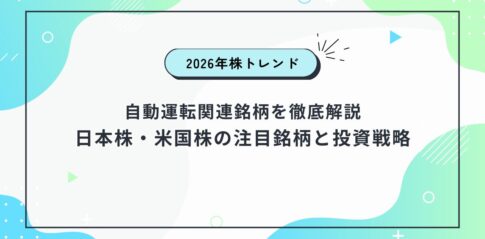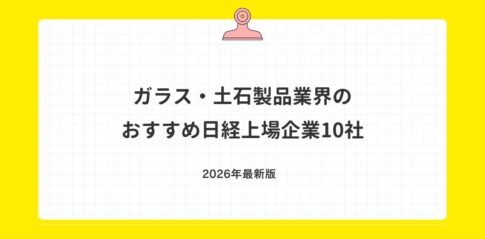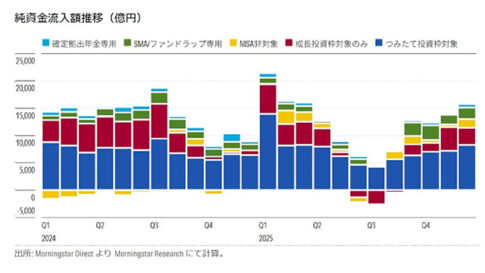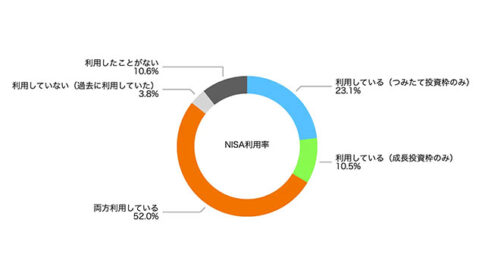日本の造船業界の現状と今後の展望
日本造船業界の歴史と現状
日本はかつて世界シェア50%を誇る造船大国でしたが、現在のシェアは韓国・中国に次ぐ3位となっています。国土交通省によると2019年の世界の新造船建造量は約7000万総トン弱で中国のシェアが約35%で首位、次いで韓国が32%、3位が日本で24%という状況です。
しかし、2025年現在、日本の造船業界は大きな転換期を迎えています。2025年06月20日(金)、日本経済新聞が「政府・自民党が国内の造船業を復活させるための政策パッケージを策定する検討に入った」と報じられました。(※1)
この記事では、政府が造船所を新設・再建し建造能力を増強する案が浮上しているとのことで、国策として造船業の日本株をご紹介いたします。
造船業界の将来性と成長見込み
日本造船工業会によると、2011年に1億総トンを超えた世界の新造船建造量は、この年を直近のピークとして22年には5590万総トンとほぼ半減した。しかし同年をボトムに23年は回復に向かっています。今後は30年代早々に1億総トンを超え、40年代半ばにかけて1億2000万総トン前後で推移する「高原状態」となる見通しとされています。
長期的な造船需要の拡大の背景にあるのは、脱炭素化・GHG(温室効果ガス)排出量削減の流れだ。2023年7月に、IMO(国際海事機関)は、従来のGHG削減戦略を改定し、50年頃までに排出ゼロと削減目標を強化したことが大きな追い風となっています。
業界再編と今治造船のJMU子会社化
2025年06月26日(木)、造船国内大手の今治造船がジャパンマリンユナイテッド(JMU)への出資比率を従来の30%から60%に引き上げ子会社化すると発表しました。(※2)今治造船はJMUの株式をIHI・JFEホールディングスから取得しIHIとJFEHDのJMUへの出資比率は35%→20%へ低下することとなります。この動きは、日本の造船業界が世界市場で競争力を高めるための重要な戦略です。
※1 出典:日本経済新聞 「国立造船所」建設を検討 政府・自民、造船業復活へテコ入れ
※2 出典:日本経済新聞 造船国内首位の今治造船、2位のJMUを子会社化 出資比率6割に
2. 造船関連株が注目される理由
政府による手厚い支援
2025年10月22日(水)の日本経済新聞オンラインで『日本の造船業の建造量倍増を目指し今治造船など国内17社でつくる業界団体「日本造船工業会」が近く3500億円の設備投資を表明する』と報じられたことがひとつのきっかけになった格好です(※3)。国策として造船業を復活させようとする姿勢が明確になっています。
※3 出典:日本経済新聞 今治造船など17社、造船能力倍増へ3500億円 日米協力にらみ国内整備
環境規制による新造船需要の増加
環境規制強化により、従来の燃料船からLNG(液化天然ガス)燃料船やゼロエミッション船への置き換え需要が急増しています。IMO(国際海事機関)の環境規制強化や炭素排出削減目標の設定も、新たな省エネルギー船や低炭素船の需要を生む要因となっています。
海運市況との連動性
基本的に、海運株の業績が好調であれば、それに伴って新造船需要も高まり、造船株にも追い風となる傾向があります。これは、海運会社が好業績を上げると、保有船舶の増強や老朽船の代替を進めるため、新たな船舶建造を発注することが多いためです。
手持ち工事量の充実
2024年、国内主要造船所は2028年前半までの船台をほぼ埋め、2025年は2028年後半~2029年納期の受注活動を進める見通しです。これにより、造船所は高利益率案件に絞った受注戦略を進めることができる状況にあります。
3. おすすめ造船銘柄10選
名村造船所(証券コード:7014)
事業概要と強み
名村造船所は、準大手の造船メーカーで、大型タンカーからバラ積み船、小型タンカーまで幅広く手掛けています。2008年に函館どつく、2014年に上場企業だった佐世保重工業をそれぞれ子会社化することで事業規模を拡大してきました。
業績と受注状況
2025年3月期末の新造船の受注残高は前年比27%増の3941憶円。環境に配慮したVLGC(LNG=液化天然ガスを運搬する大型船)2隻や大型ばら積み船10隻などを受注しており、受注状況は好調です。
2026年3月期中間決算の経常損益は11,377百万円であった。また同日発表された業績予想によると、通期の経常損益は前回予想を据え置き、28.8%減益の21,000百万円を予想しています。
投資ポイント
外資系証券では「今後の商船の新規建造関連受注において着実に単価改善が進展する」との見方もあり、中長期的な成長が期待されています。バルカーやタンカーなど多様な船種に対応できる技術力が強みです。
内海造船(証券コード:7018)
事業概要と強み
内海造船は、瀬戸内海に拠点を持つ中堅造船メーカーです。バラ積み船やコンテナ船など、多様な船種を手掛けています。
業績と財務状況
内海造船株式会社の2026年3月期第2四半期決算は、売上高が前年同期比5.0%減の216億5,200万円となる一方、営業利益は118.7%増の13億9,100万円、経常利益は259.2%増の13億5,700万円と大幅な増益を達成しました。為替相場の円安傾向や生産性向上、諸経費削減の取り組みが奏功し、収益性が大きく改善しています。
投資ポイント
売上高は微減ながら、利益率の大幅な改善が見られており、経営効率化が進んでいることが評価できます。円安の追い風も受けており、今後の業績改善が期待できる銘柄です。
三菱重工業(証券コード:7011)
事業概要と強み
三菱重工業(7011)は、日本を代表する総合重機メーカーで、エネルギー、航空・宇宙、防衛、造船など多岐にわたる事業を展開しています。造船分野では、長崎造船所を中心に、LNG運搬船や自衛隊向け艦艇の建造に注力しています。
業績と成長性
2025年3月期には売上収益が前期比7.9%増の5兆271億円、事業利益が同35.6%増の3,831億円と大幅な増収増益を達成しました。
三菱重工の防衛・宇宙部門は、25年3月期に前期比36%の増収、受注見通しも当初より9000億円上振れし約1.9兆円に達したとされており、防衛関連需要の取り込みが業績を大きく押し上げています。
投資ポイント
造船事業だけでなく、防衛やエネルギー関連など多角的な事業ポートフォリオを持つため、安定性が高い銘柄です。26.3期予想PER 49.41倍 → 27.3期予想PER 47.27倍と、依然として非常に高い水準であり、市場が将来成長を大きく織り込んでいる状態です。
川崎重工業(証券コード:7012)
事業概要と強み
川崎重工業は、陸や海、宇宙まで多彩な製品を送り出しています。造船事業では、LNG運搬船や官公庁向け艦艇などを手掛けています。
業績と成長性
川崎重工の売上収益も約5600億円で前期比約4割増となっています。防衛関連の需要増加が大きく寄与しています。
投資ポイント
26.3期予想PER 19.51倍 → 27.3期予想PER 18.17倍。実績PERレンジ(10.5〜21.1倍)の範囲内に収まっており、相対的に「妥当圏」です。三菱重工と比較してバリュエーション面で割安感があり、航空宇宙事業の回復やサービス収益の拡大によって、中期的に再評価される可能性があります。
IHI(証券コード:7013)
事業概要と強み
IHIも似たようなところですが、橋や水門といったインフラ系のものも作っています。特に強いのは航空エンジンで、もちろん戦闘機なども作っていますが、ボーイングにエンジンを納めていたりもしています。
業績と成長性
IHIも22年度に1000億円規模だった防衛事業の売り上げを30年度までに2500億円規模まで拡大する目標を掲げているなど、防衛分野での成長戦略が明確です。
IHIが持ち株比率35%、JFEホールディングスが35%、今治造船が30%の株主構成でジャパンマリンユナイテッド(JMU)に出資していましたが、今治造船によるJMU子会社化後も20%の出資比率を維持しています。
投資ポイント
26.3期予想PER 20.42倍 → 27.3期予想PER 19.44倍。実績PERレンジ(7.0〜15.5倍)と比較するとやや高めが、急回復局面にあるEPS水準を踏まえれば許容範囲です。航空エンジン事業が世界トップクラスの実力を持つため、長期的な成長が期待できます。
三井E&S(証券コード:7003)
事業概要と強み
旧三井造船。船舶用ディーゼルエンジン製造で国内首位。港湾クレーンでも世界有数。造船そのものからは2022年に撤退し、船舶エンジン事業やクレーン事業に経営資源を傾注しています。
業績と成長性
2025年3月期末の船舶エンジンを含む船舶用推進システム部門の受注高は前年比44%増の2129憶円。大型2元燃料エンジン(2種類の燃料を混合して運転できるエンジン)の受注が拡大したことなどが要因とされています。
投資ポイント
造船事業からは撤退したものの、船舶用エンジンという造船に不可欠な部品を供給しており、造船業界の成長を取り込むことができます。環境対応型の2元燃料エンジンの需要増加が追い風となっています。
ジャパンエンジンコーポレーション(証券コード:6016)
事業概要と強み
船舶用エンジンの専業メーカー。旧神戸発動機。2017年に三菱重工マリンマシナリのディーゼルエンジン事業を統合し、現社名に変更。開発から設計、製造、保守までの一貫したサービスに定評があるメーカーです。
業績と成長性
1910年創業の歴史と「UEエンジン」ブランドの強み 三菱重工業や名村造船所との資本関係 になります。2025年3月期: 売上高291億円、経常利益58億円で過去最高業績更新し、2026年3月期第1四半期: 売上高7.0%増、経常利益18.9億円で四半期過去最高。通期計画に対する進捗率32.3%(5年平均21.6%を上回る)となってます。
投資ポイント
船舶用エンジンの専業メーカーとして、造船業界の成長を直接的に享受できます。次世代脱炭素燃料エンジン(アンモニア・水素)の開発に注力しており、環境規制対応エンジンの需要増加が期待され、今後の受注拡大が見込まれます。
赤阪鐵工所(証券コード:6022)
事業概要と強み
船舶用ディーゼルエンジン専業の中堅。大型船向けのエンジンもラインナップ。リモートコントローラ(エンジンの遠隔操縦装置)、エンジンの運転状態を把握する機関監視装置を手掛ける。部品やメンテナンスも展開しています。
業績と成長性
025年3月期: 経常利益87.1%増益(58百万円)で会社予想を上回り、2026年3月期予想: 経常利益72.4%増益(100百万円)で2期連続大幅増益。2026年3月期第1四半期: 経常利益が前年同期比2.0倍に急拡大。通期計画に対して早くも170%の進捗率を達成しています。1910年創業の長い歴史を持つ企業であることもポイントの一つになります。
投資ポイント
中小型の造船会社にも対応できる柔軟性があり、新造船需要の増加に伴う受注増が期待されます。アフターサービス事業も手掛けており、安定的な収益源を持っています。
中国塗料(証券コード:4617)
事業概要と強み
塗料の大手。船舶用は国内シェア6割。世界でも第2位の規模を誇る。世界20ヶ国で事業を展開している。船底防汚塗料は、船底部に付着するフジツボや海中生物などによる表面抵抗の増大を防ぎ、燃費の向上やCO2の排出削減に貢献する。定期的な塗り替えが必要です。
業績と成長性
中国塗料株式会社の2026年3月期第2四半期決算は、主力の船舶用塗料分野での新造船向け出荷量増加や販売価格適正化により、売上高685.07億円(前年同期比8.9%増)、営業利益90.51億円(同14.1%増)と増収増益となっています。
投資ポイント
新造船だけでなく、既存船への定期的な塗り替え需要もあるため、安定的な収益が期待できます。環境対応型の船底防汚塗料の需要増加も追い風となっています。世界展開しており、グローバルな造船需要を取り込める点も強みです。
日本製鉄(証券コード:5401)
事業概要と強み
日本製鉄は粗鋼生産国内首位の大手鉄鋼メーカー。日本製鉄も造船向けの「高アレスト鋼」「HTUFF鋼」といった高機能鋼材を手掛けています。
投資ポイント
造船専業ではありませんが、造船に不可欠な鋼材を供給する立場として、造船業界の成長を間接的に享受できます。特に環境対応船や大型船に必要な高機能鋼材の需要増加が期待されます。多角的な事業ポートフォリオを持つため、安定性も高い銘柄です。
4. 造船関連銘柄(重工メーカー・部品メーカー)
造船関連銘柄とは
造船関連銘柄には、直接的に船舶を建造する造船会社だけでなく、船舶用エンジン、塗料、鋼材、電子機器など、造船に関連する部品や素材を供給する企業も含まれます。これらの関連銘柄は、造船業界の成長に伴って需要が増加するため、投資対象として注目されています。
重工メーカーの比較
日本においては、三菱重工・川崎重工・IHIが「日本三大重工業メーカー」として知られています。これらの企業は長い歴史を持ち、規模も大きな企業です。
それぞれの特徴は以下の通りです。
三菱重工業
- 日本を根底から支える業界最大手
- 売上規模、受注残高ともに3社中トップ
- 防衛・エネルギー分野に強み
- PBRも 5.38倍 と突出して高く、バリュエーション負担感が強い
川崎重工業
- 陸や海、宇宙まで。多彩な製品を送り出す
- モーターサイクル、産業用ロボットなど多角化
- 相対的に「妥当圏」。株価が既存の収益力と成長性にバランスして評価されている
IHI
- 海外からの高い評価
- 航空エンジンで世界トップクラス
- 急回復局面にあるEPS水準を踏まえれば許容範囲
舶用エンジンメーカーの重要性
船舶用エンジンは造船において最も重要な部品の一つです。環境規制の強化により、従来型のディーゼルエンジンから、LNG燃料やアンモニア燃料など、次世代燃料に対応したエンジンへの需要が急増しています。
三井E&S、ジャパンエンジンコーポレーション、赤阪鐵工所などの舶用エンジンメーカーは、この需要増加を直接的に享受できる立場にあり、注目度が高まっています。
塗料・鋼材メーカーの役割
中国塗料(船舶用塗料)
船舶用塗料は、船体の保護だけでなく、燃費向上やCO2削減にも貢献する重要な製品です。定期的な塗り替えが必要なため、ストック型のビジネスモデルを持ち、安定的な収益が期待できます。
日本製鉄(造船用鋼材)
造船には大量の鋼材が必要です。特に環境対応船や大型船には、高強度・軽量化された高機能鋼材の需要が高まっています。日本製鉄は、こうした高付加価値鋼材の供給を通じて、造船業界の成長に貢献しています。
5. 造船株投資のポイントと注意点
造船株投資のメリット
国策としての支援
政府が造船業復活に乗り出したのは、造船や人工知能(AI)など17分野を議論して2026年夏の成長戦略に反映させる方針です。造船業の再生に向けた「ロードマップ」の策定や企業が大規模な設備投資をすれば減税する制度の創設も検討すると明記しました。国からの手厚い支援があるため、業界全体の底上げが期待できます。
長期的な需要の安定性
30年代早々に1億総トンを超え、40年代半ばにかけて1億2000万総トン前後で推移する「高原状態」となる見通しであり、長期的な需要が見込まれています。
環境規制による船舶更新需要
環境規制強化により、既存の古い船舶を環境対応型の新造船に置き換える需要が継続的に発生します。これは造船業界にとって大きな追い風となります。
造船株投資のリスクと注意点
海運市況の変動リスク
造船株は海運市況の影響を受けます。なので、造船株が下落するときの傾向として、海運市況の悪化があります。バルチック海運指数など海運市況は一般的に景気より先行して動く傾向があります。海運会社の業績が悪化すると、新造船の発注が減少するため、造船会社の受注が減少するリスクがあります。
参考 Bloomberg:バルチック海運指数チャート
為替変動リスク
円高は、輸出にとってはマイナスです。円高になれば輸出がしにくい傾向になり船舶需要も減退します。需要がなく船の余剰の状態になれば造船の新規発注も減ることに繋がります。現在は円安傾向が造船業界にプラスに働いていますが、将来的に円高に転じた場合は業績にマイナスの影響が出る可能性があります。
景気変動リスク
景気が鈍化してくると輸出が減り船舶の需要も減少します。また、船舶供給が増加している状態だと市場に船が出過ぎて海運運賃の低下を招きます。世界経済の減速や貿易量の減少は、造船需要の減少に直結するため、景気動向には注意が必要です。
受注のピークタイミング
造船の建造需要は2024年がピークというお話を教えてもらいましたが、これは確かに川崎汽船の決算資料でも触れられている部分がありました。川崎汽船の資料によると新燃料船(LNG燃料炊き船)の竣工のピークが2024年、2025年の2年間がピークという見方もあります。
ただし、2025年、日本の造船業界は手持ち工事量の豊富さに支えられた心理的余裕を背景に、利益率を重視した受注戦略を進めることが予想されますとされており、受注件数が減少しても2026年度以降も利益率を維持できる可能性があります。
投資判断のポイント
手持ち工事量(受注残高)の確認
造船会社の受注残高は、今後数年間の売上を予測する上で重要な指標です。受注残高が多い企業は、安定的な業績が期待できます。
利益率の改善状況
単に受注が増えるだけでなく、利益率が改善しているかどうかも重要です。資材価格や人件費の上昇を販売価格に転嫁できているかを確認しましょう。
環境対応船の受注状況
LNG燃料船やゼロエミッション船など、環境対応型の船舶の受注状況は、将来的な成長性を測る重要な指標です。
バリュエーション(株価評価)
PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)などの指標を確認し、株価が割高か割安かを判断することが重要です。特に三菱重工のように、市場が将来成長を大きく織り込んでいる銘柄については、期待が先行しすぎていないか注意が必要です。
分散投資の重要性
造船関連銘柄に投資する際は、直接的な造船会社だけでなく、船舶用エンジンメーカー、塗料メーカー、鋼材メーカーなど、関連銘柄にも分散投資することでリスクを低減できます。
また、大手重工メーカーのように、造船以外にも防衛やエネルギー、航空宇宙など多角的な事業を持つ企業に投資することで、造船事業単独のリスクを軽減することができます。
6. まとめ
日本の造船業界は復活の兆し
日本の造船業界は、政府の強力な支援、環境規制による新造船需要の増加、業界再編による競争力強化など、複数の追い風を受けて復活の兆しを見せています。
日本造船工業会が3500億円の設備投資を表明し、政府も造船業を国策として後押しする姿勢を明確にしています。また、今治造船によるJMUの子会社化など、業界再編も進展しており、国際競争力の強化が期待されます。
長期的には、2030年代早々に世界の新造船建造量が1億総トンを超え、2040年代半ばにかけて高原状態で推移する見通しです。環境規制の強化により、既存船舶の置き換え需要も継続的に発生するため、造船業界の成長は長期的に持続可能と考えられます。
投資対象としての造船関連銘柄
造船関連銘柄は、直接的な造船会社だけでなく、船舶用エンジン、塗料、鋼材など幅広い選択肢があります。それぞれの企業の特徴を理解し、自身の投資スタイルに合った銘柄を選ぶことが重要です。
安定性を重視するなら
- 三菱重工業、川崎重工業、IHIなど大手重工メーカー
- 多角的な事業ポートフォリオによるリスク分散が可能
成長性を重視するなら
- 名村造船所、内海造船など造船専業の中堅メーカー
- 受注残高の増加と利益率改善が期待される
安定収益を重視するなら
- 中国塗料(定期的な塗り替え需要)
- 船舶用エンジンメーカー(アフターサービス事業)
間接的な恩恵を受けたいなら
- 日本製鉄など鋼材メーカー
- 造船需要の増加を間接的に享受
今後の注目ポイント
造船関連銘柄への投資を検討する際は、以下のポイントに注目しましょう。
短期的な注目ポイント(2025年~2026年)
- 政府の造船業支援策の具体的な内容と実施状況
- 各社の2025年度以降の受注状況と利益率の推移
- 為替相場の動向(円安は追い風、円高は向かい風)
- 海運市況の変化(バルチック海運指数などの動向)
中長期的な注目ポイント(2027年~2030年代)
- 環境対応船(LNG燃料船、アンモニア燃料船、水素燃料船)の開発と普及状況
- IMOの環境規制の更なる強化の可能性
- 業界再編の進展(今治造船のJMU子会社化に続く動き)
- 世界の造船受注シェアの変動(中国・韓国との競争)
最終的な投資判断は慎重に
造船関連銘柄は、国策としての支援や長期的な需要増加が見込まれる魅力的な投資対象ですが、海運市況や為替、景気変動などのリスクも存在します。
投資を行う際は、以下の点に注意しましょう。
- 複数の銘柄に分散投資する
造船専業会社だけでなく、関連銘柄にも投資してリスクを分散 - 受注残高と利益率を定期的にチェック
四半期決算ごとに業績を確認 - 海運市況や為替の動向を注視
バルチック海運指数や為替レートの変動に注意 - 長期的な視点で投資
短期的な株価変動に一喜一憂せず、業界の成長を見据える
造船業界の未来に期待
日本の造船業界は、一時期の苦境を乗り越え、新たな成長期を迎えようとしています。環境規制への対応、デジタル化、自動化など、技術革新も進んでおり、日本の高い技術力を活かせる分野です。
政府の支援、業界再編による競争力強化、環境対応船の需要増加など、複数の追い風が吹いている今こそ、造船関連銘柄への投資を検討する好機かもしれません。
免責事項:本記事は情報提供を目的としており、特定の銘柄の購入を推奨するものではありません。投資判断は自己責任で行ってください。株式投資にはリスクが伴い、元本割れの可能性があります。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。